好きこそ物の上手なれ。
熟達するには、楽しめるようになることが肝心。
楽しく勉強ができるように、
要点をわかりやすく解説するブログです。
この記事では、
令和7年度沖縄県調理師試験│解答速報│解説をお伝えします。
毎週金曜日に更新される記事をお読みいただき、
一発合格を目指しましょう。
\調理師免許の試験問題を毎日投稿中/
解答速報
⚠️ここでお示しする解答は、すきうまブログ独自の見解で作成したもので、各資格試験の主催者とは一切関係ありません。解答速報に関する各資格の主催者へのお問い合わせはご遠慮ください。
⚠️科目ごとに更新していきますので、しばらく経ってからリロードしてご覧ください。
解説
公衆衛生学:問1
次のうち、疾病予防の段階と手段に関する組み合わせとして、正しいものはどれか。
(1) 一次予防─健康診査、人間ドック
→二次
(2) 一次予防─理学療法、職場の配置転換
→理学療法は三次予防
(3) 二次予防─食事節制、予防接種
→一次
(4) 三次予防─社会復帰、リハビリテーション
問2
次のうち、環境汚染と公害に関する語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
(1) 二酸化窒素─ 環境基準は設けられていない。
→設けられている
(2) 新潟水俣病─ 四大公害病のひとつである。
(3) BOD─ 化学的酸素要求量のことである。
→COD
(4) イタイイタイ病─ 原因は光化学オキシダントである。
→カドミウム
問3
次の職場の健康管理に関する記述のア〜ウに入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
事業者は、ア第66条に基づき全労働者に対してイを、有害な業務に従事する者に対してウを実施することになっている。
アイウ
(1) 労働安全衛生法─特殊健康診断─一般健康診断
(2) 労働基準法─特殊健康診断─一般健康診断
(3) 労働安全衛生法─一般健康診断─特殊健康診断
→正しい
(4) 労働基準法─一般健康診断─特殊健康診断
問4
次のうち、公来衛生に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) わが国の法第25条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公来衛生の向上および増進に努めなければならない」とある。
(2) ウインスロー教授は、公来衛生を「地域社会の組織的な努力により疾病を予防し、生命を延長し、肉体的・精神的健康と能率の増進をはかる科学であり、技術である。」と定義している。
(3) ヘルスプロモーションは、人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセスである。
(4) 保健所(保健センターを含む)は、公衆衛生活動の中心として、地域住民の生活環境の向上と健康の保持・増進に重要な役割を果たしている。その設置主体は都道府県のみである。
→政令指定都市や中核市、特別区も設置することができる
問5
次のうち、感染症に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) 感染症が発生するには、感染源、感染経路、感受性の3条件がそろうことが必要である。
(2) 症状の重さ、感染力や危険度などから1~5類感染症に分類されている。
(3) 蚊など(ベクター)の刺により、病原体が体内に侵入することにより感染することを飛沫感染という。
→ベクター感染、媒介動物感染
(4) 感染症対策上、大切な点は各個人が疾病に対する感受性の低下(抵抗力の向上)を図るため予防接種を行うことである。
問6
次のうち、疾病予防の方法として、正しいものはどれか。
(1) ある程度のストレスをためて、1日あたり2~3時間の睡眠をとる。
(2) 間食を増やす。
(3) 朝食は数日に1回程度でよい。
(4) 喫煙をしない。
→正しい
問7
次のうち、ネズミ、衛生害虫に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) ネズミやハエ、ノミ、シラミ、ゴキブリなどの衛生害虫は感染症の原因となる細菌やウイルスなどの病原体を媒介する。
(2) ネズミや衛生害虫などによる健康被害を防止するため、建築物環境衛生管理基準では防除に関する規定が設けられている。
(3) ネズミの駆除は、進入口の閉鎖や隠れ場所を無くすことが基本で、食品の密封保管や毒えさを置くと逆効果になる。
→効果的
(4) 蚊は日本脳炎、マラリア、フィラリア症、デング熱などの感染症を媒介する。
問8
次のうち、環境衛生に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) 採光とは、太陽光を室内に取り入れて明るさをとることである。
(2) 人工光源で日常生活や給食室、調理室に適当な照度は、50ベクレル以上とされている。
→ルクス
(3) シックハウス症候群は、ホルムアルデヒドやトルエンなどの化学物質が。
原因となる。
(4) シックハウス症候群は、ダニやカビ、湿度、心理社会要因など、さまざまな要因が複雑に関係している。
問9
次のうち、職場の健康づくりに関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) 厚生労働省によると、わが国の健康診断結果の有所見率の割合は、5割を超えている。
(2) わが国は、心身両面にわたる健康増進のためトータル・ヘルスプロモーション・プランを推進している。
(3) トータル・ヘルスプロモーション・プランは、産業医、運動指導担当者、産業保健指導担当者、産業栄養指導担当者、心理相談担当者などを含めたチーム指導が進められている。
(4) ストレスチェック制度は、事業者が労働者に対して心理的な負担の程度を把握し職場環境の改善につなげるものだが、事業場における導入は義務化されていない。
→ストレスチェック制度は、労働者が50名以上いる事業場では年1回の実施が義務付けられている
食品学:問1
次のうち、植物性食品に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) 植物性食品は、一般的にたんぱく質や脂質は少ないが、大豆のように、たんぱく質や脂質が多いものもある。
(2) 植物性食品のうち、穀類、いも類は、エネルギー源とならない。
→なる
(3) 植物性食品は、砂糖類と油脂類を除いて食物繊維が多く含まれる。
(4) 植物性食品は、一般的にビタミン、無機質(ミネラル)に富んでいる。
問2
次のうち、香辛料とその特性・用途の組み合わせとして、正しいものはどれか。
香辛料─特性・用途
(1) しょうが─辛味性。薬味、におい消し、菓子類に。
→正しい
(2) バニラ─矯臭性。シナモン、クローブ、ナツメグをあわせたような香り。
→と同じく甘い
(3) わさび─着色性。色と香味を利用。煮込み料理への色と香付け。
→辛味性
(4) サフラン─辛味性。ひき肉料理やハムなどに。
→着色性
問3
次のうち、アレルギー表示に関する記述として、正しいものはどれか。
(1) アレルギー表示の方法は、特定原材料等を一括表示のアレルギー欄内に記載する必要があり、原材料欄内には記載を省略できる。
→できない
(2) アレルギー表示の方法として、一括表示枠外に別途強調表示する取り組も義務化された。
→は任意である
(3) アレルギー物質は、重篤度・症例数の多い21品目を特定原材料として、表示を義務づけている。
→8品目
(4) アレルギー物質の表示制度は、食物アレルギーを持つ人の健康被害の防止を目的としている。
問4
次のうち、酒の製造方法による分類と品目の組み合わせとして、正しいのはどれか。
分類─品目
(1) 醸造酒─リキュール
→混成酒
(2) 蒸留酒─ワイン
→醸造酒
(3) 混成酒─梅酒
(4) 醸造酒─ウイスキー
→蒸留酒
問5
次のうち、食品の貯蔵・加工に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) 納豆は、大豆を煮てから乳酸菌を繁殖させてつくる。乳酸菌の作用で大豆の消化がよくなり、その過程でビタミンCが増加する。
→納豆菌
(2) かつお節は代表的な焙乾品で、本枯節は、カツオブシカビをかび付けすることで、かびが産生する酵素によって類独特の風味が醸成される。
(3) 一般に、肉類、魚類、卵類を一度塩蔵した後に燻煙する燻煙法は、塩蔵の防腐効果に加えて、燻煙による乾燥、また、その煙の成分により表面の微生物の増殖を抑える。
(4) 食塩、砂糖の濃厚液には脱水作用があり、微生物の繁殖を防ぐ。肉類、魚類、野菜類は塩漬けとし、果実類は砂糖漬けとする。
問6
次のうち、食品の特徴と性質に関する記述として、正しいものはどれか。
(1) 穀類は、外皮、胚芽、胚乳の3部分からできていて、外皮と胚芽には、でんぶんが多く、胚乳には、「たんぱく質、脂質、ビタミンB」が多い。
→胚乳、外皮と胚芽
(2) ごま、アーモンドは、脂質を50%以上含有し、たんぱく質も約20%含んでいる。無機質としては、カルシウム、リン、ごまではさらに鉄などが多い。
(3) 肉類は、食肉処理(と殺)直後は、自己消化により、やわらかくなると同時にうま味が増すが、時間が経つとかたくなる。
→かたく、やわらかく
(4) 嗜好飲料は、リラックス効果など精神面への効果よりも、栄養的な価値が大きい。
→小さい
栄養学:問1
次のうち、国の栄養施策に関する記述として、正しいものはどれか。
(1) 食生活指針は、適切な食事内容を示したもので、食料資源や環境への配慮は含まれていない。
→いる
(2) 食事バランスガイドのコマは、主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の5つに区分される。
(3) 国民健康・栄養調査は、文部科学省が毎年実施しており、栄養素等摂取状況や身体状況が明らかにされている。
→厚生労働省
(4) 食事バランスガイドでは、料理の量をメッツの単位で示している。
→つ(SV)
問2
次のうち、炭水化物に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) エネルギー源として重要であり、1gあたりで約4kcalのエネルギーを発生させる。
(2) 主な二糖類は、ブドウ糖、果糖、ガラクトースである。
→単糖類
(3) 難消化性炭水化物(食物繊維)は、腸のぜん動運動を起こして排便を促進する作用がある。
(4) エネルギーとして消費するために、ビタミンB1が必要である。
問3
次のうち、無機質(ミネラル)に関する組み合わせとして、誤っているものはどれか。
ミネラル─生体内での関わり─主な食品
(1) 鉄─酸素の運搬─レバー、あさり
(2) カリウム─神経伝達や筋収縮
(3) 亜鉛─核酸やたんぱく質合成─肉類、魚介類
(4) 銅─神経鎮痛作用─食塩、牛乳・乳製品
→ミネラル
問4
次のうち、栄養生理に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) 食欲を調節する摂食中枢と満腹中枢は、間脳の視床下部に存在する。
(2) 食欲は、個人の食習慣や嗜好の影響も受ける。
(3) 受副腎皮質ホルモンであるコルチゾールは、血糖値を上昇させる働きがある。
(4) 副腎髄質から分泌されるアドレナリンは、コレステロールから生成されるステロイド系のホルモンである。
→カテコールアミン系のホルモンである
問5
次の脂質の消化吸収に関する記述のア~ウに入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
中性脂肪(トリグリセリド)は、膵液りパーゼの作用を受けて分解されアの上皮細胞に吸収されるが、一部は中性脂肪に再合成された後、キロミクロンに包まれてイに入り、胸管を通って血液中に入る。水溶性のMCFA (中鎖脂肪酸)は、ウ に入り肝臓へ運ばれる。
ア イ ウ
(1) 小腸─リンパ管─門脈
→正しい
(2) 胃─門脈─リンパ管
(3) 胃─リンパ管─門脈
(4) 小腸─門脈─リンパ管
問6
次のうち、消化吸収率に関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) 食物繊維を多く含む食品では低下しやすい。必
(2) 糞便中に含まれる消化液や腸内細菌の死がい等の量を内因性損失量と呼び、見かけ上の消化吸収率の計算式で使用される。
→真の消化吸収率
(3) 動物性食品は植物性食品に比べ消化吸収率が高い。
(4) 食品の種類や加工法、調理法等によって異なる。
問7
次のうち、ビタミンAに関する記述として、誤っているものはどれか。
(1) 欠乏症に、夜盲症があげられる。
(2) 過剰症に、脚気、神経系障害(ウェルニッケ脳症など)があげられる。
→頭痛、発疹、肝障害、骨や皮膚の異常など
(3) β=カロテンは、ビタミンAの前駆体である。
(4) 脂溶性ビタミンに分類される。
問8
次のうち、ライフステージと栄養に関する記述として、正しいものはどれか。
(1) 乳児期に、母乳の代替品として用いられる育児用ミルクは、母乳成分と同等の成分が含まれているため、感染症予防の観点からも安心して使用できる。
(2) 幼児期は、消化器官が発達し、機能が十分であるため、1日3度の食事のみで必要量が満たせる。
→1〜2回の間食が推進されている
(3) 成人期は、脂質の過剰摂取につながりにくく、脂肪の質に留意する必要がないため、魚介類よりは獣肉類の摂取を心がけると良い。
→質にも留意する必要がある
(4) 高齢期は、嚥下障害の調理の工夫として、油脂類の利用が効果的である。
問9
次のうち、病態と栄養に関する記述として、正しいものはどれか。
(1) 鉄乏性貧血では、鉄の吸収を高めるビタミンDを積極的に摂る。
→ビタミンC
(2) 糖尿病では、血糖値の上昇を抑える食物繊維を積極的に摂る。
(3) 急性肝炎では、脂質を主体としたエネルギーの摂取を要する。
→肝機能障害時
(4) カシオコア (クワシオルコル)は、エネルギー欠乏性の栄養障害である。
→たんぱく質
食品衛生学:問1
問2
問3
問4
問5
問6
問7
問8
問9
問10
問11
問12
問13
問14
問15
調理理論:問1
問2
問3
問4
問5
問6
問7
問8
問9
問10
問11
問12
問13
問14
問15
問16
問17
問18
食文化概論:問1
問2
問3
次回予告
この記事では、
令和7年度沖縄県調理師試験│解答速報│解説をお伝えしました。
次回更新時も勉強される方は、
- こちらのページをブックマーク
- ブログ名【すきうまブログ】を覚えて、次回検索
どちらかをおすすめします。
初めて当サイトをご覧になった方は、調理師の試験対策として、暗記すべき要点をまとめた記事もありますので、下記の記事から順にご覧ください。
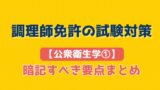
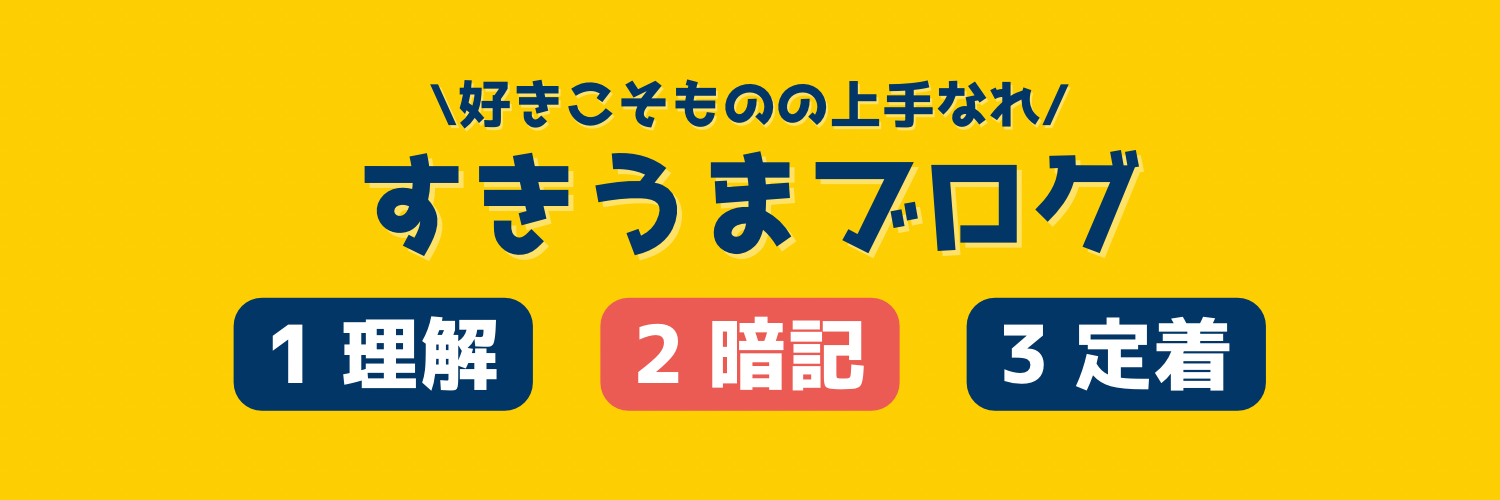
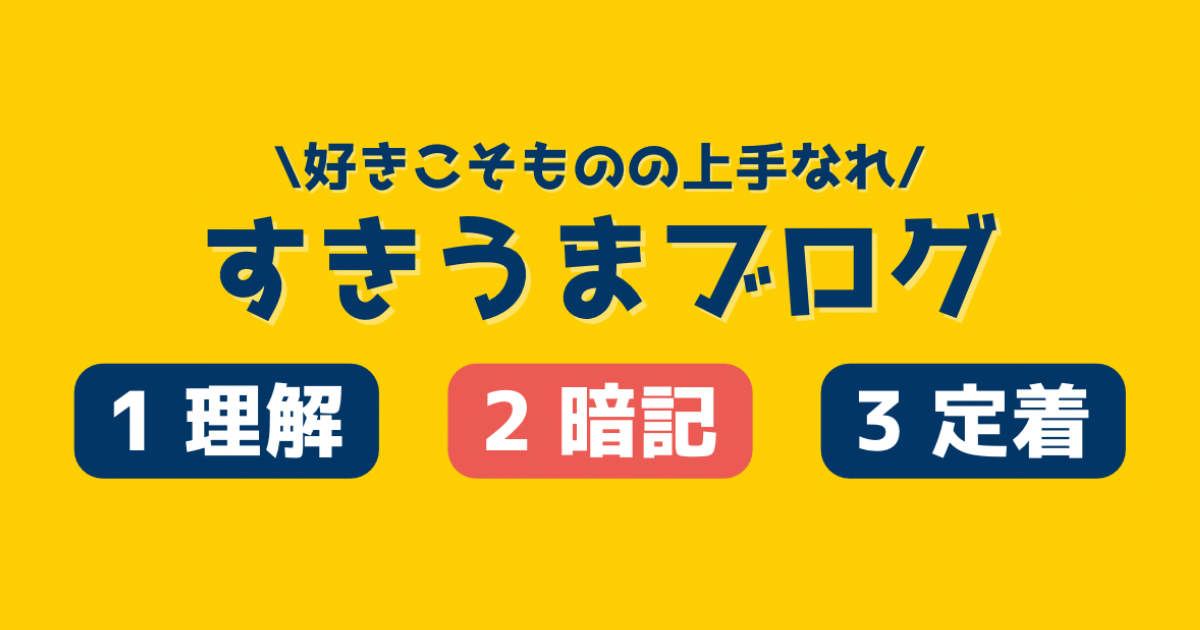
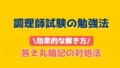
コメント